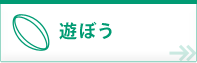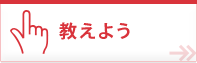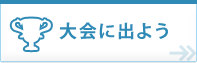港区タグラグビー指導者講習会 レポート
|
9月5日(日)、猛暑日が続く中、港区・港区立青山小学校を会場として(財)日本ラグビーフットボール協会主催のタグラグビー指導者講習会が開催されました。 港区と(財)日本ラグビーフットボール協会は基本協定を締結し、スポーツを通じて豊かな地域社会を創造することを目指し「スポーツまちづくりプロジェクト」を推進しておりますが、本講習会も、タグラグビー指導者の育成と共にタグラグビーの地域普及の活性化に努めることを目的として実施されました。 当日は総勢24名の参加となり、講師には、(財)日本ラグビーフットボール協会普及・競技力向上委員会 タグラグビー部門長の鈴木秀人氏にお越し頂きました。講習は第1部と第2部とに分割され、第1部では実際に体を動かしながらのタグラグビーの実技講習を、第2部ではタグラグビーが導入されるまでの背景や、タグラグビーの指導ポイント等を座学による講習で学ぶこととなりました。 午後12時半。本講習会開催に向けてご協力をしてくださった港区体育指導員協議会 会長の小堀章氏の挨拶を開会の挨拶とし、早速実技講習へと入りました。
まずはグルーピングから始まり、参加者を全4チームのグループに分けました。タグの配布を行い、正しいタグの付け方の説明が終わると、準備運動を兼ねた2人組でのタグ取りが始まりました。「タグ!」の声かけから取り方まで参加者は一つ一つ丁寧に実践し、その後のチーム対抗のタグ取り合戦が終わる頃には、体も温まり、タグラグビーの基本動作の1つであるタグ取りを体で学ぶことができた様子でした。メニューはそこからボールを使ったものへと移行し、
等の基本動作メニューが実施され、最後はタグラグビーゲームまでを楽しみながらの実技講習となりました。 このように、指導ポイントを知ることで、全ての動作に意味があるのだと気づくことができる有意義な実技講習となりました。 第2部の講習では大きなテーマとして、「なぜタグラグビーが注目されるようになったのか」ということが挙げられました。そこで、ボールゲームの授業をめぐる問題から問題解決の突破口としてタグラグビーが注目された経緯、そして注目された理由となるタグラグビーの魅力についての説明が行われました。 ボールゲームの授業をめぐる問題点のひとつに運動嫌い・苦手な子の増加がありました。この問題は深刻化しており、昭和世代の参加者達は特に納得をしながら講義を聞いている様子でした。また、特に感嘆した様子で講義を受けていた内容は、タグラグビーと他のスポーツとを実際にデータを取って比較する、というものでした。ここにタグラグビーの魅力の1つがぎっしりと詰まっているというのが、確かに裏付けられました。
最後の質疑応答では、タグラグビーの備品がどこで手に入るのか等、今後のタグラグビーの導入と実践に意欲的な姿がみられました。それも全て、本講習会においてタグラグビーの魅力が伝わった成果なのではないでしょうか。 9月とはいえだまだ暑い中、参加してくださった先生方・指導員の方々・青山タグラグビー教室参加保護者の方々、本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。また、ご尽力してくださった港区体育指導委員協議会から講師の鈴木先生をはじめとした全ての関係者の皆様にこの場を借りまして、深くお礼申しあげます。 平成22年9月9日(木) 菊池 |